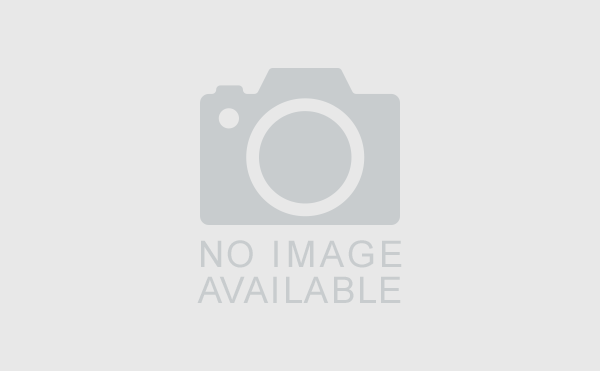電力「kW(キロワット)」のマイナスについて
はじめにまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電力(kW) | 消費・供給の大きさを示す単位 |
| マイナスkW | 系統への電力供給(逆潮流) |
| 保護装置 | 停電時の逆送防止・設備保護 |
| PCS | DC→AC変換・同期制御・保護機能 |
| 周波数/電圧 | 系統全体で一定に維持される重要要素 |
1. 電力(kW)とは?
電力(kW)は、電気のエネルギーがどれだけの速さで使われているかを表す単位です。
1kW=1000Wで、1秒あたりに1000ジュールのエネルギーを消費または供給することを意味します。
- 家電や照明などが電気を使う → プラスのkW(消費電力)
- 発電して電気を送り出す → マイナスのkW(供給電力)
2. マイナスのkW(逆潮流)とは?
太陽光発電などで発電した電力が自家消費を上回ると、余った電気が電力会社の系統へ流れます。これを「逆潮流」といいます。
その結果、メーター上ではマイナスのkWとして表示され「建物が電気を使う側」から「電気を送る側」に変わっているということです。
3. 系統連系と安全装置の確認
電力会社の系統と連系して運転する場合は、安全装置の設置と動作確認が非常に重要です。
| 装置名 | 役割 |
|---|---|
| 逆潮流防止装置(RPR) | 電力会社に過剰な電力が流れないよう制御 |
| 過電圧保護装置(OVP) | 電圧上昇時に設備を保護 |
| 系統連系保護装置 | 系統異常や停電時に発電を自動停止(感電防止) |
停電時に発電を続けると、電力会社の作業員が感電するおそれがあります。
連系保護装置の定期試験は必ず実施してください。
4. 停電時の動作と自立運転
通常、系統連系型の太陽光発電設備は停電時に自動停止します。これは、逆潮流を防ぎ、作業員の安全を守るための仕組みです。一部の設備には「自立運転モード」があり、停電時でも特定の回路に電力を供給できます。ただしこの場合、系統から完全に切り離した状態でのみ使用可能です。
5. 周波数(Hz)の基礎知識
電気の「周波数」は、1秒間に電圧が何回変化するかを示す値です。
日本では地域によって異なります。
| 地域 | 周波数 | 主なエリア |
|---|---|---|
| 東日本 | 50Hz | 北海道・東北・関東 |
| 西日本 | 60Hz | 中部・関西・中国・四国・九州 |
機器やパワーコンディショナーは、必ず設置地域の周波数に合わせる必要があります。
周波数が合っていないと、同期不良や機器故障を引き起こすことがあります。
6. パワーコンディショナー(PCS)の役割
太陽光パネルが発電するのは「直流電力(DC)」ですが、
家庭や工場、電力会社の系統で使うのは「交流電力(AC)」です。
パワーコンディショナー(PCS)は、このDCをACに変換し、
電圧・周波数を電力会社の系統に合わせる重要な装置です。
主な機能
- 直流 → 交流変換(インバータ機能)
- 電圧・周波数同期制御
- 逆潮流制御・出力抑制対応
- 保護機能(過電圧・過電流・連系遮断など)
点検・選定ポイント
- 変換効率は90%以上を目安に。
- 地域の周波数(50/60Hz)に適合しているか確認。
- 電圧上昇抑制機能があること。
- 送電線電圧の変動に追従できる系統追従性能を確認。
設定や保護機能に誤りがあると、停電・ノイズ・誤動作の原因になります。
7. 電圧と周波数の安定化(発電所側の制御)
発電所では、系統全体の安定を保つため、周波数制御と電圧制御を常時行っています。
(1) 周波数制御
発電機の回転速度によって決まり、次の装置で制御します。
- ガバナー(調速機):タービン回転数を自動調整し、需要変動に対応。
- AFC(自動周波数制御):中央制御室で発電量を調整して全体の周波数を一定に維持。
- 同期運転制御:複数の発電所が協調し、周波数を一致させる。
周波数は「全員で同じテンポでこぐ自転車」のようなもの。
1つの発電所が速く回れば全体が乱れ、系統不安定の原因となります。
(2) 電圧制御
電圧は「電気を押し出す力の強さ」です。
以下の方式で制御・安定化しています。
- 励磁制御(AVR):発電機の磁界を制御して電圧を一定に。
- 変圧器タップ制御:送電距離・負荷変動に合わせて電圧を補正。
- 無効電力制御:コンデンサやリアクトルで電圧の安定を確保。
8. 定期点検と保守のポイント
安定した運転と安全確保のため、以下の点を定期的に確認してください。
- PCSの周波数・電圧設定が地域に適合しているか
- 系統連系保護装置・過電圧保護装置の動作試験
- 電圧上昇抑制機能が正常に働いているか
- 放熱ファン・通気口の清掃(熱劣化対策)
- 端子・配線の緩み、腐食チェック