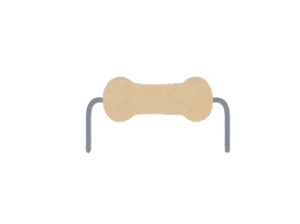IEC 保護クラス I、II、III 機器とは
クラス I
危険な電圧がかかる部分と人が触れる部分の間を基本絶縁で分け、さらに保護接地(アース)で感電を防ぎます。プラグは3本ピン(L:ライブ、N:ニュートラル、E:アース)で、金属筐体が多いです。
例:工場だとアース線がついているドリルや溶接機、接地極付コンセントで絶縁破壊しても安全になります。
注意点:クラス I 機器を使用する際は、アース接続が正しく行われているか確認が必要です。接地が不十分だと、絶縁故障時に感電リスクが高まります。
クラス II
クラス II は基本絶縁に加え、二重絶縁があります。二重絶縁は、絶縁が一重破損しても、もう一重の絶縁が残るため、安全性が保たれます。アース接続は不要で、安全性を高めるため、プラスチック筐体が多く使われている。
例:工場の事務所や作業現場で使われるノートパソコン充電器もクラス II に該当。
クラス III
クラス III はSELV(Safety Extra-Low Voltage、安全特別低電圧)またはSELV-E回路のみに接続されるか、内部にSELVまたはSELV-E電源だけを持つ機器です。SELVは、電圧が50V AC以下または120V DC以下で、通常の条件下で感電の危険がほぼないとされています。このため、基本的な絶縁や保護接地を必要としません。
例:工場のコードレスドリルやインパクトドライバーで、低電圧(例えば12Vや18V)のものが該当します。感電のリスクがほぼなく、クラス III に分類されます。
まとめ
- クラス I:「アース線がついている機器」。金属製のドリルや溶接機のように、アース線が絶縁が壊れたときの安全を確保します。
- クラス II:「二重の絶縁がある機器」。プラスチック製の電動工具や充電器のように、アース線が不要で、プラスチックで二重に守られています。
- クラス III:「低電圧しか使わない機器」。バッテリー工具で、電圧が低いので特別な安全対策が不要です。