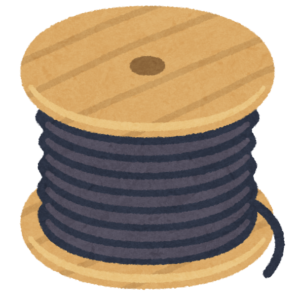電気工事士は低圧電気取扱業務の特別教育はいる?いらない?
結論ですが、低圧(交流600V以下、直流750V以下)の電気設備の充電部分の作業に従事する場合は、電気工事士の資格を所有していても低圧電気取扱業務の特別教育は必要です。例えば、電源を入れた状態での点検・測定・修理・接続作業・操作などが該当します。
低圧電気取扱業務
労働安全衛生規則第36条第4号に定める危険(感電の恐れのある)な業務に該当すれば、電気工事士や電験の資格に関係なく、特別教育の受講義務が生じます。
<学科>
| 低圧の電気に関する基礎知識 | 1時間 |
| 低圧の電気設備に関する基礎知識 | 2時間 |
| 低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 1時間 |
| 低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 2時間 |
| 関係法令 | 1時間 |
| 学科合計 | 7時間 |
<実技>
| 低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 7時間 |
⚡ “電気工事士の資格がある”=“感電リスクを防止できる教育を受けている” ではない。
⇒ 法的には、「特別教育の受講」が義務になります。
講習会で受けるかWEBで受けるか。
低圧電路で開閉操作以外の業務を行う場合には、実技7時間をうける必要があるので講習会を受けることをお勧めします。
・関東電気保安協会
https://www.kdh.or.jp/study/low_7h.html
電気工事士の資格が必要な作業
☑配線器具の取り付け・取り外し・結線
☑金属製ボックスの取り付け・取り外し
☑配電盤の取り付け・取り外し
☑電線相互接続
電気工事士の資格が不要な作業(軽微な工事、電気工事士法施行規則第1条で電気工事から除外されている)
☑電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事。
☑電圧600V以下で使用する電気機器又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事。
☑電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取りはずす工事。
☑インターホーン、火災感知器、などの2次電圧が36ボルト以下の二次側の配線工事。